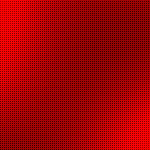Mステで氷川きよしを観る日が来ようとは誰が想像しただろう。
去年の今頃、私はまだ彼の変化を知らなかった。
しかし彼はどんどん進化する。
「限界サバイバー」は演歌歌手のほんのご愛嬌だと感じた人達の観念を見事に裏切ってアーティストの道を歩み始めた。
昨年後半よりいくつか出したオリジナルの次元を完全に越えたのが、この「ボヘミアン・ラプソディ」だ。
「ボヘミアン」は言わずもがな、Queenの世界的名曲である。
この曲でフレディがそれまでのロックの常識を打ち破ったように、氷川きよしも彼のイメージを打ち破った。
彼も話すようにこの曲は難曲である。
難曲中の難曲。
この曲をカバーする人が少ないのは、この曲が余りにも衝撃的でフレディの歌声無くしては歌えないほどの強烈なイメージを私達に与えたからだ。
「オペラとロックの融合」
まさに音楽ジャンルにおいて、真逆とも思われていた二つのジャンルの融合を試みた楽曲であり、その意外性が完全に成功した楽曲でもある。
この曲を歌うには表現力と何よりも声の強さが必要になる。なぜならこの曲はフレディが自分自身が歌うことを想定して作られた曲だからだ。それゆえ、彼以外の歌声がこの曲を歌うことを曲自体が頑として拒否しているように思えるほど、フレディの歌声と楽曲のイメージは同一化している。
その聖域とも言える部分に氷川きよしは足を踏み入れたのだ。
単に「いい曲だと思った」という言葉の裏側には並々ならぬ覚悟と挑戦する気持ちがあったはずである。
この楽曲を歌うことで、完全に彼は今までの自分のイメージを潔く脱ぎ去りたかったのかもしれない。
手放すものが大きければ大きいほど、手に入れるものも大きくなる。
彼の今日の歌は、珍しく緊張が見えた。
彼ほどのベテランであり、数々の賞を総ナメにして来た人間ですら、この楽曲の大きさの前にはひれ伏し、慄き、足が竦むのかもしれない。
珍しく気負いが見えた。
そう感じたのは高音がフラットしたからだ。
彼の高音がフラットするのを聞いた記憶が私にはないほど、いつも彼の高音はまるで発声の見本のように音程が正確だ。だから珍しいと思った。
高音がフラットするというのは息が入りきっていないか、支えが上がってしまっているかのどちらかで、それは強度の緊張から来る歌手のよくありがちな現象の一つである。
彼ほどの歌手でもこの曲を披露するというのは緊張を伴うものなのだと思った。
しかし、それ以外の部分。例えば語りの部分においては、非常に言葉が練られており流暢で、そこにはNHK で歌った時よりも格段の進化が見られ、彼がこの楽曲を自分のものとして消化していることを感じさせた。
またオペラからロックに変わっていく部分では、声の張りも声質のチェンジも申し分がない。
声質のチェンジや音程の高低を難なくこなす部分は、やはりさすがだと感じさせた。
おそらくアルバム収録にあたってよく歌い込んだのではないかと思われた。
気負いが見られた前半のオペラ部分に対し、後半のロック部分では何も言うことがない。彼の持ち味を十分生かし、自由にダイナミックに歌い切るロックの世界を存分に表現したと感じる。
ポップスアルバム発売まであと数日だが、そこには彼の様々な音楽性が納められているだろう。
氷川きよしが演歌を20年、歌い続けてなお捨てられなかったポップスやロックへの音楽性が十分に発揮されているに違いない。
彼の新しい歩みは、間違いなく始まっているのだ。
追記
「氷川きよしの新しい挑戦」と言うタイトルで、ミュージック・ペンクラブのHPにエッセイ記事を書かせて頂いています。ミュージック・ペンクラブは、日本の音楽評論家などの集まった団体で、ボヘミアン・ラプソディの日本語歌詞を書かれた湯川れい子さんも所属されており、さらに氷川さんは「限界突破✖️サバイバー」で新しいものに挑戦する姿勢と功績が認められ、2019年度のミュージック・ペンクラブ作品賞を受賞されています。
もし、まだ記事をお読みでない方がいらっしゃいましたら、下記をクリックすると読むことが出来ますので、あわせてどうぞ。
関連記事
- 投稿タグ
- Mステ, VocalReview, ボヘミアン・ラプソディ, 氷川きよし