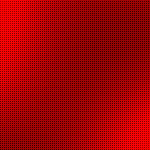クイーンの代表曲「ボヘミアン・ラプソディ」
昨夜のNHK「うたコン」で氷川きよしがカバーしたのを聴いた。
この曲は、昨年末に彼が自身のコンサートが初披露した様子を情報番組で少しだけ聴いた記憶がある。その時も書いたように思うが、カバー曲を歌えば必ず賛否両論が巻き起こる。誰もが納得するカバー曲など存在しない。
それぐらい、オリジナル曲はその歌手のものであり、楽曲は歌声と共に聴衆の記憶の中に残る。オリジナル以外の歌手が歌う時点で、それは誰が歌おうと必ず賛否両論の嵐に巻き込まれる。
カバー曲というものはそういうもので、それでもあえてなお歌うところに歌手のある種の覚悟が必要になる。
この曲もご多聞に漏れず、昨年も今回も賛否両論が巻き起こっていると聞いた。
この曲は非常に難曲だ。
まず、楽曲構成が大きく3つに分かれる。映画のシーンにもあったように「オペラ」。そうオペラの要素がふんだんに取り入れられている。全編は、オペラのアリアともいうべきソロのゆっくりとしたメロディーをたっぷりとした声量で歌うことが求められる。そして展開部の早い語り口の部分では、音程の高低が繰り返され、声のコントロールが非常に難しい。アップテンポの中で言葉の処理とリズム感、チェストボイスからヘッドボイスまでの音域を行ったり来たりするメロディー。歌い手にとっては難所だ。そして、最後、浪浪したスローテンポに戻った楽曲をたっぷりとした声量で歌い続けることが要求される。
これだけのテクニックを要求される楽曲は、フレディ自身が作ったから歌えたのであって、他の誰もが歌えるものではない。それぐらい、フレディのための楽曲である。そして彼の歌声があったからこそ成立した曲なのだ。
湯川れい子が日本語訳詞を許可された時点で、「ボヘミアン・ラプソディ」はクイーンの楽曲であって、フレディの手から離れたものになった。
氷川きよしが歌う「ボヘミアン・ラプソディ」は氷川きよしのものであって、それ以外の何物でもない。
冒頭の歌い出しから、それはもう彼以外の歌ではなかった。
日本語で歌うことの難しさにあえて挑戦する。
言葉の処理、語尾の響きの抜け感、そして、ファルセットの使い方。
どれをとっても演歌で培ったものは影を潜め、ポップス歌手として大曲に挑む姿があった。
彼なら歌える。
彼だから歌えたのかもしれない。
42歳になっても彼の歌声は非常に「鳴り」がいい。
パンと押し出した歌声はストレートで「鳴り」がよく真っ直ぐに声が伸びていく。前半から後半のサビにかけてのたっぷりとした音量を要求されるフレーズで、彼の歌声は枯れることがない。
彼だからへばることなく歌えるのだ。
どれだけ歌っても掠れもしない歌声は、彼が20年、しっかりと歌い込んできた証のようなもの。そうでなければ、後半でスタミナ切れを起こす。
演歌の時の低音部の唸りのような響きは、この曲ではほとんど姿を現わさない。その代わりに響きを抜いたファルセットとフレーズ最終音節の処理が顕著だ。
今まであまり見かけなかった彼の新しいテクニックがたくさん顔を出す。
以前も誰かのカバー曲の時に書いたように思うが、歌手がカバー曲を歌うことで成立するのは、その楽曲を自分の曲として消化している場合だけだ。
オリジナルをそのままなぞっただけでは、単なる猿真似でしかない。
オリジナルを尊重しながら、一旦、自分のものとして楽曲を自分の身体に入れ消化した上で、自分のオリジナル曲として歌えたものだけがカバー曲として成立すると私は思う。
確かにオリジナルの歌声があって楽曲は成立する。しかし、楽曲は誰のものでもなく、単に五線上に書かれた音の羅列である。その音の羅列に命を吹き込むのが歌手であり、そこにそれぞれのオリジナル性が生まれてくると考える。
氷川きよしの「ボヘミアン・ラプソディ」はそういう点で、彼のオリジナルとして成立している。
フレディーの歌声を模倣することなく、氷川きよしの歌声で彼の「ボヘミアン・ラプソディー」の世界が構築されている。
「皆さんにこの歌をどうしても日本語で届けたくて歌います」
この彼の言葉が全てである。
「日本語で届けたい」
この想いが彼の「ボヘミアン・ラプソディー」の原点である。
そう思った。
関連記事
- 投稿タグ
- うたコン, ボヘミアン・ラプソディ, 氷川きよし