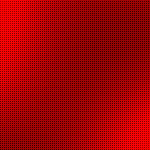手越祐也が「富士インターナショナル・スピードウェイ」で国歌を独唱した歌を聴いた。
僅か1分余りのこの歌に彼のソロ歌手としてのスタンスが現れていると感じた。
国歌「君が代」は、非常に単純な歌である。
誰もが知るこの単純な歌は、しかしながら、日本の歌の特徴をそのまま映し出している。
それは、先ず、一音に一文字がつく、という日本語の歌の特徴そのもので作られている点だ。
この歌は非常にスローな歌である。
また長音符ばかりの符割りで、一見何を歌っているのかわからないほど、言葉がこの長音符のせいでバラバラになる。
そういう点で非常に難しい曲とも言える側面を持つ。
多くの歌手が、様々なスポーツやイベントの場面で、国歌独唱を歌っているが、アカペラで歌うこの歌は、ある意味、歌手の実力を丸裸にする。
それゆえ、歴代、どの場面でも安定した歌唱力の持ち主が選ばれてきた。
この容易に見えて実は難曲であるこの曲を手越は、非常にオーソドックスな歌い方で歌った。
そこにこの人の歌手としてのスタンスが見え隠れする。
今回、彼のこの歌を聴いて先ず感じたのは、言葉のタンギング。
このタンギングが、非常に正確だということだった。
タンギングというのは、元々は管楽器を演奏する際の舌を用いる奏法の総称のことで、舌の動きによって音の出だしを明確にするテクニックのことを言うが、歌の場合は、言葉の出だしの発音の明瞭さを現すのに私は用いている。即ち、言葉の最初のアタックのことで、これが彼の場合は、非常に明確に発音されていたのが印象的だった。
日本語の場合、何度かブログに書いたが、言葉の発音は、50音によって構成されている。
即ち、日本人の意識の中に、言葉は50種類の文字の構成によって成り立っているという感覚があり、それはそのまま50種類の発音があると認識している。
「あ」「い」「う」「え」「お」という母音だけでなく、「か」は「か」の発音、「さ」は「さ」の発音という風に50音は、それぞれ独立した文字であり、当然、それぞれの文字の発音も独立したものを持っているという認識になる。
これが26文字のアルファベットを組み合わせて一つの単語を作りあげている、という認識の外国人との大きな違いになる。外国人の場合、あくまでも単語は、全てが26文字の組み合わせによって作られており、「KA」は「か」ではなく、K➕A、「SA」は「さ」ではなくS➕A、という風に、全ての文字は子音と母音の組み合わせで成り立っているという認識を持つ。その為、発音もあくまでも子音と母音の組み合わせという認識であり、子音をハッキリ発音することで、何の文字なのかを認識するのである。
これが「か」はあくまでも「か」の発音であり、K➕Aの発音であるという認識を持たない日本人との大きな違いになる。
しかし、この認識は、洋楽、いわゆる西洋音楽の符割りによって作られている楽曲にとっては、一音に一文字という言葉のつけ方になり、スローな楽曲や長音符が連続するメロディーラインの場合、一つの言葉のまとまりがバラバラになり、何を歌っているのか、どこで言葉が切れるのかが分からなくなる、という特徴を持つ。
例えば、「君が代」の歌詞で子供が一番意味がわかりにくい音節に、
「いしの いわおとなりて」というフレーズがあるが、音符割りが、「いしのー」「いわおとなりて」という割り振りになっている。そうなるとよく子供心に、「おとなり」って何?岩のお隣のこと?岩のお隣ってどういうこと?などと思ったものだ。
これは「いわおとなーりて」の一文字ずつが一拍ずつの符割りになっている為、何も考えずに歌った場合、一瞬、おとなりって何?みたいに錯覚するのである。これは一重に、「いわお」即ち「巌」という文字を平仮名にして一文字に一拍ずつの音符を割り振った為である。
この部分をどのように処理するかが、この歌の最大の興味でもある。
多くの歌手がこの部分の言葉のタンギングに苦労するからであり、ゆったりとしたテンポの中で、言葉が最も流れて行きやすいフレーズでもある。
何人かの歌手の国歌独唱を聴いたが、皆、「いわおとなりて」とワンフレーズで歌っていた。
しかし、このフレーズを彼は、「いしのー」「いわおと、なりて」と歌ったのである。
即ち、「いわお」と「なりて」という風に、「と」という言葉をあくまでも二つの単語「いわお」「なりて」の繋ぎ言葉の助詞として処理したのである。
こうすることで、ハッキリと聴き手には、言葉が一つずつの塊として届く。
これが彼の歌のスタンスの全てに通じていると私は感じる。
彼の言葉の処理は、全て、文節で言葉を感じとって歌っていると思われる。
それゆえ、各単語のタンギングが非常に明確だ。
この歌でも「君が代」の「き」のK音、「よ」のY音、「千代に八千代に」の「ち」のCH音、「さざれ」の「さ」のS音という風に、非常に子音をハッキリと発音するタンギングになっているのである。
これが全体にゆったりとしたこの曲にハッキリとしたメリハリを与え、言葉のタンギングを鋭角に掘り下げることによって、野外にいる観衆の耳に明確に言葉が届く、という効果を生み出している。
「君が代」は、単純で単調な曲で音楽が横に流れていくという習性を持つ。それだけに、野外で聴いた場合、歌詞の言葉が耳の中で流れていくのだ。
それをタンギングを縦に深く切り込むことによって、一つ一つの言葉が明確に立ち、野外にいる聴衆の耳の中に言葉が明瞭に残っていくのである。
声量は申し分ない。
声の伸びも言うことがない。
「君が代」を歌うのに選ばれる歌手は、声量が豊かで、伸びやかな声の持ち主が多い。
その条件を彼は十分兼ね揃えている。
あとは、どう表現するか、だ。
ここに歌手としてのそれぞれの持ち味が反映される。
彼はこの歌を非常に丁寧に歌っていた。
広い会場の隅々まで自分の声が届くように、フレーズの最後までブレスが途切れないように、コントロールされた歌声だった。それは、歌の最後の最後の言葉の納め方、ブレスの切り方によく現れている。
「こけのー」「むーすーまーでー」
この最後の「で」の「DE」のE音の切り方が、プツンと切れないように慎重にブレスを納めていくところに、彼が曲の最後まで丁寧に歌い切ろうとする意思が見え隠れしていたと私は感じた。
これが歌手手越祐也の「歌」に対するスタンスなのだと思う。
歌手は「歌う機会」が与えられてナンボの世界である。
それは一方的に配信する世界とは違って、目の前に観客のいる世界だ。
その観客に「歌を届ける」のが歌手の仕事である。
彼は、事務所を出て以来、その機会に十分恵まれているとは言い難い。
だからこそ、そういう機会を与えられたなら、大切にする。
たった一度のやり直しのできないワンテイクの世界だ。
その緊張感を彼は楽しんで歌っているように見えた。
それは、どんな不遇な状況でも、コツコツと積み上げてきた確かなものから来る自信のようにも見えた。
それだけのパフォーマンスが出来るだけのことを積み上げてきた証拠でもある。
もっと彼が歌う機会があればいい、と純粋に思った。
ライブで彼がどのようにステージを構成していくのか、非常に興味が湧いた。
そんな機会があればいいと思う。

![ちゃんみな『日本と韓国、世界を音楽の力強いメッセージで繋いでいくトリリンガルラッパー』(前編)人生を変えるJ-POP[第45回]](https://vocal-review.com/wp-content/uploads/2024/09/1709167774406-oFIDonJtea-150x150.jpg)