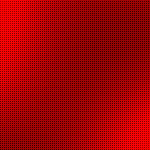氷川きよしは確実に進歩している。否、進化している。
彼がもうずっと出演を熱望していたというNHKの「SONGS」
この番組に出演できるということが彼の中での「ポップス歌手として認められた」という一つの免罪符だったのかもしれない。
20年間「演歌界の貴公子」として多くのファンを獲得し、歌手としての存在と支え続けて貰ったファンをポップス歌手へ転身することである意味裏切ることになるという彼の中の一種の罪悪感のようなものを「SONGS」の出演は救ったように感じる。
NHKの看板番組への出演は、転身が社会的に認めらたという自信に繋がったように感じた。
「変わりたい。いつまでも同じ場所にいられない。変わっていかないといけない」
「40過ぎて限界突破して次のドアを開けたい」
そう彼は言った。
演歌の貴公子としてだけでなく、常に演歌界のトップを走り、牽引してきた彼だが、歌手としての本心はどこかで満足しきれていなかったということになる。これがポップスから演歌に変わるのなら、これほどの葛藤はなかったかもしれない。
演歌は日本人の心のルーツ、という音楽界での特別な存在感が日本人本来のジャンルへの転身をすんなりと受け入れる土壌がある。しかし、ポップスという洋楽のジャンルに転身していくことは、ある種の裏切り行為のように捉えられかねない懸念を持つことが彼の中での長年の葛藤だったのではないだろうか。
彼の転身は最初、小さなものだった。
「限界突破✖️サバイバー」という楽曲に限られたものだった。
「ボヘミアン・ラプソディを観て、歌詞を見てたら涙が出てきた。彼は凄い葛藤があったんだろうな、と」
「常にナチュラルでいたい。ナチュラルにいきたいというふうに思う。キーナチュラル」
「ボヘミアン・ラプソディ」のフレディの生き方が歌手氷川きよしの背中を押したのだ。
そうやって彼は自分の気持ちを隠さなくなった。
演歌歌手氷川きよしとして作られたイメージで生きていくよりも、自分らしく、ありのままの自分で生きていくことを選んだのだ。
枷が外れた彼は、自由に大空を飛び回る蝶になった。
楽曲「Papillon」はさなぎから蝶に転身した彼そのものを描いている。
自分て何だろう。自分が本当に歌いたい歌に巡り会えていない気がした、という彼は、限界突破で歌いたい歌に巡り合い、ボヘミアン・ラプソディで自分らしく生きていくことを決意した。
「SONGS」で歌った彼はどの曲も明らかに進化している。
特に一番の変化は言葉の処理に気負いがなくなったことだ。
概して演歌歌手の場合、ありがちな言葉に力を必要以上に入れて強い声で歌うという習癖は彼の中から完全に抜け落ちようとしている。そしてどの音域も非常に素直に発声されている。
そこには彼の「ありのままに自分らしくナチュラルにいたい」という思いがそのまま歌声に反映されているように感じる。
元々滑舌がよく、張りのある恵まれた歌声を持って生まれている彼が本来、歌うべき場所に戻った。
そんな気がする。
これからの彼の一曲一曲は、彼のありのままの気持ち、そのものだろう。
彼が20年、心の中で培ってきた彼本来の音楽性がポップスというジャンルで爆発していくに違いない。
「人と違っていい。1人1人、みんな違う。
人と違うことをおかしいとか言われる筋合いはない」
そう彼は言った。
人間は本心を誤魔化して生きていくことなど出来ない。
彼の歌手としての本心が満足するものを歌うことが彼が歌手としての道を全うすることに繋がっていく。
彼の転身は私達にそう教えてくれている。
※
ミュージック・ペンクラブのHPのエッセイ欄に彼に関する私の書いたエッセイが掲載されています。
この記事と合わせて読んで頂くと彼の変化がより理解していただけるように感じます。
読まれる方は下記からどうぞ。
関連記事
- 投稿タグ
- SONGS, ボヘミアン・ラプソディ, 氷川きよし, 限界突破✖️サバイバー