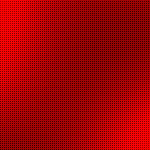氷川きよしが歌った「ボヘミアン・ラプソディ」が年末に物議を呼んでいた。演歌歌手のカテゴリーを外した彼がクイーンのカバー曲を歌ったということ、そして日本語訳で歌ったということがその理由らしい。
全曲の音源を聴いたわけではないが、部分的に聴いた限りにおいては、非常に質の高いカバー曲になっていると感じた。
「ボヘミアン・ラプソディ」は大ヒットした映画と共にフレディ・マーキュリーの歌声が今も耳の中に残る。クイーンの楽曲は彼の歌声なしには成立せず、彼の歌声のイメージがそのまま楽曲のイメージとなって多くの人の記憶に残る。
私は彼らの楽曲をリアルタイムで聴いた記憶がなく(その頃はクラシック漬けの毎日)映画によって彼の歌声のファンになった。彼の歌声の中毒になり、映画の高揚感と彼の歌声が重なり、6度、映画館に足を運んだ。今でも最後のシーン「Live Aid」の臨場感を味わいたいと思っている。それぐらい彼の歌声に嵌った。なぜならそこには彼の魂があったからだ。
湯川れい子が日本語の訳詞をつけ、日本語訳で歌うことが許されたという今回のカバー曲は、氷川きよしだからこそ許されたのだと感じる。
フレディの心の葛藤がそのまま氷川きよしの虚像と実像との狭間で葛藤した姿にオーバーラップするからだ。
言葉の端々から零れ落ちるような歌声はそのまま彼の魂の叫びそのものに感じた。
多くの葛藤を抱えながらも20年間、走り続けた彼だからこそ、今自分を解放しようとする気持ちがそのまま歌声に現れるからだ。
カバー曲は当然、オリジナル曲を好む人達の批判に晒される。
しかし、楽曲はオリジナル歌手のものではなく、すべての人のものでもある。
単に譜面に描かれた音符と言葉の羅列が、声という楽器に載せられた瞬間に命を吹き込まれ、唯一無二の歌へと変わっていく。そこには歌手の魂そのものが宿っていく。
楽曲は誰のものでもない。
その音楽の尊厳を犯さない限り、誰が歌っても構わないはずだ。
カバー曲は、楽曲という素材を使ってそれぞれが調理する料理のようなものである。
題材、素材は同じでも、作り手によって出来上がった品物は、それぞれの味付けに変わり、唯一無二のものとなっていく。その料理のどれを好み、どれをチョイスするかは聴き手に委ねられているものだ。
優れた楽曲を歌いこなすには、それなりに歌手のスケールを求められる。
歌手がどれだけの器と引き出しを持っているかによってカバー曲の質は決まる。
氷川きよしは歌うべくして「ボヘミアン・ラプソディ」を歌った。
彼が歌うことを許されたということは、彼の歌手としての器が楽曲に見合っていたということになる。
彼なら楽曲の尊厳を壊さないと認められたということだ。
彼のカバー曲のジャンルは多岐に渡る。
この経験がさらに彼を歌手として飛躍させることは間違いない。
そして彼の楽曲に対するスタンスが変わらない限り、どんな曲でも彼のカバー曲になり得る可能性を持つ。
そう思った。
関連記事
- 投稿タグ
- カバー曲, フレディ・マーキュリー, ボヘミアン・ラプソディ, 氷川きよし