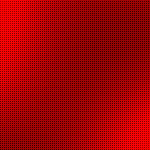道頓堀にある大阪松竹座で「紅ゆずるトークショー」を観てきた。
今年2月の「紅ing」以来、8ヶ月ぶりの生紅の姿だった。
トークショーは冒頭のレーザー光線による「紅」「降臨」という大きな文字と共に彼女の姿がステージに浮かびあがる。
歓声はあげられないから大きな拍手!!!
そんな感じで始まった。
冒頭は彼女が1人で。
話好きの彼女の事、どうしても時間が推すらしく、タイムウォッチを持たされてのトークの始まりだった。
3分間の持ち時間が終わったところで司会者が登場。
元々、彼女のファンクラブにも入っていたという毎日放送の女性アナウンサーの司会で数々の質問に答えながら、トークが進められるという形だった。
私が彼女を推す最大の理由は、彼女の持つオーラだ。
宝塚の男役は、退団後、非常に難しい選択の中に放り込まれる。
それは男役を辞めて、どのような路線で自分を売り出していくかという選択だ。
このブランディングがうまく行かないと、その後の輝きを失ってしまう人が多い。
歌って踊れ、芝居も出来る彼女達は、ミュージカルの分野に進出するのが王道である。多くが東宝ミュージカルなどの舞台を経験して、その後も、ミュージカルの世界に生きる人が多い。
昨今のミュージカルブームでは、非常に重宝がられ、ニーズも高いだろう。
しかし、彼女は「女優」の道を選んだ。
彼女のアンチから言わせれば「歌が上手くない。ダンスも大した事ない。ミュージカルなんて出来ない」
だから女優しか道はない、とでも言いたいのだろう。
しかし、私は彼女のファンであるという贔屓目をはずしても、アンチが叩くほどの理由を彼女の歌やダンスに見出せない。なぜなら、彼女には、持ちたくても誰もが持てない、スター性が備わっているからである。
即ち、彼女には舞台人として一番必要な「華」が備わっているのだ。
この「華」は宝塚時代、男役のトップスターだった人には皆備わっているのものである。
しかし、退団後はそれを持ち続ける人は非常に稀だ。それはなぜかと言えば、彼女達が、「男」から「女」への転換を迫られるからである。
それが当然であり、転換していかなければ、仕事の幅は非常に狭くなる。それゆえ、かつての演目でヒーローを演じたものから退団後にはヒロインの役へと転換し、女性として演じる演目も多い。
しかし、彼女は「女優」の道を選んだ。
彼女はあくまでも「紅ゆずる」である事を選んだのだ。
男でもなく女でもなく「紅」になる。
彼女の選択は、「紅ゆずる」というブランドを守り続ける事。
これが非常に上手く行っている、と私は昨日、彼女の姿を観て思った。
彼女は自分をブランディングする能力が非常に高い。
決して歌も踊りも得意でなかった下級生の時代から、トップに上り詰めていくのに、彼女は決して諦めなかった。
決して自分の能力を疑わなかった。
この自己肯定感の強さが、全てを引き寄せていく。
この肯定感の強さは、芸能人としては必要不可欠なものになる。
孤独な芸能界では、自分を信じることしか自分を前に進めることは出来ない。
落ち込んだり、凹んだりしながらも、最後は自分を信じる力が備わっているものだけが生き残っていく。
彼女は、持ち前のブランディング能力で、自分をしっかり前へ打ち出していける。
「あー、やっぱり私はこっち側の人間やったんやなー、と思います」とステージに立ち、スポットライトを身体一杯に浴びて彼女はそう言った。
「ピン!このピンがいいねん!」
そう言って、ピンスポットを一身に浴びて笑顔だった。
そう、彼女にはピンスポットが合っている。
何より彼女自身が、光合成して、光り輝いている。
どんな場所にいても必ず這い上がってくる。
この強さが「紅ゆずる」の持ち味だ。
ポジティブで決して諦めない。
「前向きに生きなアカン!」と自分に言い聞かせ、何もかもを引き寄せていく。
女優になってもそのオーラは変わることがなく、舞台人として光り輝いている。
いつも彼女を観ると元気になる。
彼女から学ぶことは多い。
人生を諦めないこと。
夢を諦めないこと。
彼女の存在そのものが多くの人に夢や希望を与えるのだ。
そんな彼女だからこそ、次々と主役の舞台やミュージカルが決まっていく。
アンチが叩いていたブロードウェイミュージカル「エニシング・ゴーズ」
単に歌が上手くても、女優として光り輝かなくては、客は呼べない。
宝塚ファンだけでなく、それ以外の客層も呼び込めるだけの力があると判断されたからこそのキャスティングだ。
男役の音域から解放されれば、彼女の当たりと鳴りのいいチェストボイスは、ステージに鳴り響くだろう。
ステージを観て元気が貰える。
また頑張ろうと思う。
それが本当に夢を与える人である。
そんな彼女は、やっぱり私のイチオシだ。
※
半年以上の閉鎖を経て再開された大阪松竹座の公演は、非常にコロナ対策の取られたものだった。
きちんと検温をして消毒をし、会場へ入っていく。
いたるところにスタッフが配置され、非常に細やかな気配りがされた会場だった。
やっぱりリアルな場所はいい。
舞台と客席の呼吸が聞こえるその場所は、やっぱり格別なものだった。